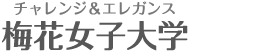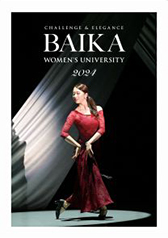現代人間学研究科
心理臨床学専攻
充実のカリキュラム内容と実習体制。
臨床心理士・公認心理師への道を
力強くサポートします。
心理臨床学専攻では、カウンセラーや心理療法士となるために必要な専門的な知識と技術を修得し、臨床心理士・公認心理師の資格を持つ人材の育成をめざしています。臨床対象が拡大化し、症例が複雑化する臨床現場で役立つ、高度な専門性と実践力を身に付けるため、きめ細かい指導体制で研究の発展をサポートしていきます。
目標
本専攻は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の第一種指定大学院に指定されています。また、公認心理師受験資格にも対応しています。本学の特色であるキリスト教の精神を生かし、一人ひとりの人間の尊厳を大切にすることを第一に考え、かつ実践能力を持った「臨床心理士」「公認心理師」を養成します。
この専攻の特色
-
-

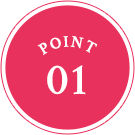
-
豊富な実践経験
学内実習施設としての附属心理教育総合相談センター、および本学が提携している多種多様な学外実習施設において、療育プログラムや認知行動療法を含む幅広くかつ豊富な心理臨床の実践経験を積み重ねることが可能です。
-
-
-

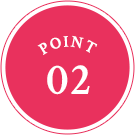
-
多種多様な選択科目、
特に子どもと芸術に重点化
[子ども領域(子育て支援・小児医療・不登校支援など)]と[芸術領域(描画・箱庭・身体表現・音楽など)]をはじめとする、多領域にわたる選択科目を用意しています。
-
-
-

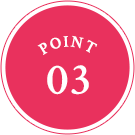
-
医学や基礎心理学もカバー
実践・研究・教育経験の豊富な臨床心理学専門の教員スタッフだけでなく、医学(精神医学・小児医学)や他領域の心理学を専門とする教員スタッフの配置により、幅広い人間理解と臨床心理士・公認心理師資格取得を全面的にバックアップします。
-
カリキュラム[2025年度]の編成
(心理臨床学専攻修了要件)
必修科目12科目26単位、A~E群の選択必修科目から各群2単位、F群から心理実践実習ⅠA、B・ⅡA、B・ⅢA、Bのうち4科目を含む4単位以上計14単位以上、合計40単位以上を修得します。
また、自分の専門領域に合わせて心理臨床学演習(ゼミ)を履修し、修士論文を作成します。
以上の修了要件は臨床心理士受験資格要件でもあります。
なお、出願時に2年で修了することが難しいことが予測される場合には、3年間もしくは4年間の履修を希望することができます。
| 必修 | 臨床心理学特論Ⅰ、臨床心理学特論Ⅱ |
|---|---|
| 臨床心理面接特論Ⅰ、臨床心理面接特論Ⅱ | |
| 臨床心理査定演習Ⅰ、臨床心理査定演習Ⅱ | |
| 臨床心理基礎実習Ⅰ、臨床心理基礎実習Ⅱ | |
| 臨床心理実習Ⅰ、臨床心理実習Ⅱ | |
| 心理臨床学演習Ⅰ、心理臨床学演習Ⅱ | |
| A群 | 心理統計法特論 |
| 臨床心理学研究法特論 | |
| B群 | 人格心理学特論 |
| 発達心理学特論 | |
| 認知心理学特論 | |
| 音楽心理学特論 | |
| C群 | 社会・産業心理学特論 |
| 家族心理学特論 | |
| 犯罪心理学特論 | |
| D群 | 精神医学特論 |
| 障害児(者)心理学特論 | |
| 心身医学特論 | |
| E群 | 遊戯療法特論 |
| 描画・箱庭療法特論 | |
| 心理療法特論 | |
| 学校臨床心理学特論Ⅰ | |
| F群 | 学校臨床心理学特論Ⅱ |
| 心理実践実習ⅠA、ⅠB | |
| 心理実践実習ⅡA、ⅡB | |
| 心理実践実習ⅢA、ⅢB | |
| 心理実践実習ⅣA、ⅣB |
<公認心理師受験資格要件科目>
| 資格取得カリキュラム | 授業科目名 |
|---|---|
| 保健医療分野に関する理論と支援の展開 | 精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開) |
| 福祉分野に関する理論と支援の展開 | 障害児(者)心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) |
| 教育分野に関する理論と支援の展開 | 学校臨床心理学特論Ⅱ(教育分野に関する理論と支援の展開) |
| 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 | 犯罪心理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開) |
| 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 社会・産業心理学特論(産業・労働分野に関する理論と支援の展開) |
| 心理的アセスメントに関する理論と実践 | 臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践) |
| 心理支援に関する理論と実践 | 臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践) |
| 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 | 家族心理学特論(家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践) |
| 心の健康教育に関する理論と実践 | 発達心理学特論(心の健康教育に関する理論と実践) |
| 心理実践実習ⅠA、ⅠB | 心理実践実習ⅠA、ⅠB |
| 心理実践実習ⅡA、ⅡB | 心理実践実習ⅡA、ⅡB |
| 心理実践実習ⅢA、ⅢB | 心理実践実習ⅢA、ⅢB |
| 心理実践実習ⅣA、ⅣB | 心理実践実習ⅣA、ⅣB |
| 心理実践実習Ⅴ | 臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習Ⅴ) |
(実習時間について)
心理実践実習Ⅰ~Ⅴの総実習時間数は450時間以上とする。そのうち、担当ケースについての実習時間を270時間以上、学外実習機関における実習時間を90時間以上とする。
主要科目
Pick UP
-
臨床心理学特論Ⅰ
河野
臨床心理学の歴史を紐解きながら、心理支援についての理論や実践の基礎を学びます。臨床心理学を取り巻く状況の変化、その現代的課題にも理解を深めながら、臨床家としての基本的態度を身につけ、センスを養うことをめざします。
-
臨床心理学特論Ⅱ
今井
欧米ではスタンダードな心理療法として定着している認知行動療法(CBT)は、日本においては未だ定着していません。しかしながら、厚生労働省は疾患ごとのマニュアルを作成し、効果的な治療法としてCBTの適用を推奨しています。本講義ではCBTの理論と実践について基礎から解説したうえで、新世代のCBTについても理解を深めます。
-
臨床心理査定演習Ⅰ(心理アセスメントに関する理論と実践)
伊丹・柴田
査定の意義、その効用と限界などについて学び、そのうえで、各種発達検査の理論と技法について実践を交えながら体験的に習得します。
-
臨床心理査定演習Ⅱ
岡本・田島
各種心理検査(質問紙法・投影法)の実施法、効用と限界を学び、さらに、ロールシャッハ・テストの実施法とスコアリングおよび解釈について学びます。また、病院臨床におけるWISCなど知能検査の所見の書き方や行動観察の重要性について学びます。
-
臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践)
河野
カウンセリングの定義に始まり、こころの構造、カウンセラーに必要な基本態度、初回面接の進め方、カウンセリングの過程、治療(転移)関係、関連機関との連携などについて学びます。
-
臨床心理面接特論Ⅱ
柴田・今井
具体的臨床事例に触れながら、留意点、諸問題に関する対応、終結のあり方などについて学びます。また、個人心理面接だけでなく認知行動療法など各種技法についても習熟します。
-
臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ
河野・田島
心理教育総合相談センターで実際に事例を担当するに際して必要な心構え、技能、倫理、具体的手順などについて学びます。例えば、ロールプレイを通じて個々のシチュエーションでの適切な対応を学んだり、初回面接に陪席してカウンセリングへの導入のあり方やカウンセラーの基本的態度や見立ての方法などの具体例について学びます。
-
臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習Ⅴ)・Ⅱ
柴田・森本・河野・山本・岡本・今井
ケースカンファレンスでは、大学院生が担当する各種心理検査・発達検査・心理面接・プレイセラピーなど個々の事例について、見立て、対応、過程、意義、問題点などを検討します。臨床心理士資格を有する全教員と全大学院生、研究生によって、多面的、総合的な検討を行います。インテークカンファレンスでは、教員によって行われる受理面接の報告、バウムなどについて、見立て、対応などを検討します。また、センター実習、病院実習、学校実習、療育、SST各論についてアセスメント、個別及び集団における心理支援、記録作成の仕方、家族支援、守秘義務や連携などについて学びます。
-
心理臨床学演習Ⅰ・Ⅱ(ゼミ)
柴田・三雲・森本・岡本・河野・今井
担当教員指導のもと、文献講読やディスカッション、予備調査を取り入れながら、統計解析ソフトSPSSなどを活用した調査データ解析を行い、修士論文の作成を進めていきます。
-
障害児(者)心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開)
田島
自閉症スペクトラム障害などの発達障害に関する理解を深め、集団、個別療育の理論、方法について事例の検討を通して学びます。
-
心理実践実習ⅡB
田島・森本・今井・河野
発達障害傾向のあるお子さん対象の療育実習です。子どもの発達状態を観察及び発達検査によって精査し、子どもの具体的な困り感を把握して、これらをもとに個別の支援計画を作成します。また、療育担当児童との関係づくり、保護者へのフィードバックについても実習体験します。
-
描画・箱庭療法特論
河野・柴田
表現の治療的意義についての基本的理解のもと、表現療法の中でも描画療法や箱庭療法の理論と方法について、実習体験や事例の検討を通して学びます。
教員の紹介
| 教授伊丹 昌一 |
学校臨床心理学特論Ⅱ、臨床心理査定演習Ⅰ 特別支援教育、学校心理学、子育て支援、発達障害児・者の支援、障害のある子の保護者支援 |
|---|---|
| 教授今井 正司 |
臨床心理実習Ⅰ,Ⅱ、心理臨床学演習Ⅰ,Ⅱ、心理実践実習ⅠA・B,ⅡA・B,ⅢA・B、ⅣB、臨床心理学特論Ⅱ、臨床心理面接特論Ⅱ 認知行動療法、マインドフルネス、神経行動教育学 |
| 教授柴田 由起 |
臨床心理実習Ⅰ,Ⅱ、臨床心理面接特論Ⅱ、心理臨床学演習Ⅰ,Ⅱ、臨床心理査定演習Ⅰ、心理実践実習ⅠA,ⅡA,ⅢB,ⅣA・B、描画・箱庭療法特論 描画療法、コラージュ療法、児童期思春期の心理臨床、学校臨床 |
| 教授瀧本 優子 |
心理実践実習ⅣA 精神保健福祉、ソーシャルワーク実践、SST(Social Skills Training) |
| 教授三雲 真理子 |
認知心理学特論、音楽心理学特論、心理臨床学演習Ⅰ,Ⅱ 音楽活動や運動・創作活動などによる介入効果の検討、 |
| 教授森本 美奈子 |
臨床心理学研究法特論、臨床心理実習Ⅰ,Ⅱ、心理実践実習ⅠA,ⅡA・B,ⅢA・B,ⅣB、心理臨床学演習Ⅰ,Ⅱ、家族心理学特論 認知症患者と介護家族への心理教育介入、精神的回復力や自己成長力と |
| 准教授大芝 宣昭 |
心理統計法特論 霊長類(ニホンザル・チンパンジー・ヒト)における系列学習の比較、ニホンザルによる将来の |
| 准教授岡本 智子 |
遊戯療法特論、心理臨床学演習Ⅰ,Ⅱ、臨床心理査定演習Ⅱ、心理実践実習ⅠA・B、IVB、臨床心理実習(心理実践実習Ⅴ) 心理療法におけるセラピストの想像活動、深層心理学、夢分析 |
| 准教授田島 真知子 |
障害児(者)心理学特論、発達心理学特論、臨床心理基礎実習Ⅰ,Ⅱ、心理実践実習ⅠA,ⅡA・B,ⅢA・B、心理実践実習ⅣA・B 障がい児(者)の特徴や支援方法(発達障がいや知的障がいを中心に)、早期療育の重要性、 |
| 准教授福井 斉 |
社会・産業心理学特論 自尊感情、産業組織心理学(集団間葛藤が個人的・集合的自尊感情に及ぼす影響、 |
| 講師河野 一紀 |
臨床心理実習Ⅰ,Ⅱ、心理実践実習ⅠA・B,ⅡA・B,ⅢA,ⅣB、臨床心理基礎実習Ⅰ,Ⅱ、臨床心理面接特論Ⅰ、臨床心理学特論Ⅰ、描画・箱庭療法特論、心理臨床学演習Ⅰ,Ⅱ ラカン派精神分析、青年期の心理臨床、学生相談 |
在学生の声
W.Mさん(武蔵野大学 人間科学部 人間科学科卒業
梅花女子大学院 現代人間学研究科 心理臨床学専攻在学中)
今振り返ると、私は小さいころからこころについて考えることが多かったように思います。自分の気持ちから他者の感情について、「どうしてだろう」という興味・関心が 芽生え、自然と大学の進路選択では心理学を専攻していました。またこの探求心は、人のこころに留まらず、動物と人間の関係性にまで広がっていき、心理学と動物の癒しが融合した動物介在について研究をしたいと思い、ここ梅花女子大学院への進学を決めました。
本学は、臨床心理士や公認心理師の資格取得に向けたカリキュラムはもちろん、将来、心理士として即戦力になれるよう構成された豊富な実習を、1年時から積めることが大きな強みである思っています。入学後間もなく始まるSSTや学校実習、心理相談センターでの託児・陪席、また後期には療育や多様なケースの担当など、充実した内容に、時に追いついていくのに手一杯になったり、手探りから始める実習で思い悩むこともありました。ただ、ふと振り返ると、その経験から着実に日々成長している自分を感じることができ、同時に大きなやりがいを得ることができます。もちろん、そのためには日々の勉学が欠かせませんが、自身が目指す心理士像に向けて、共に努力し、志を互いに尊重し合える同期、多くの臨床現場で得た豊富な知識をご指導くださる先生方、そして一期一会で出会えるクライエント様から学べる環境によって、日々一歩一歩前に進んでいく事ができています。これからも、このような環境を大切にしていき、努力を惜しまず、自らが描く心理士像になれるよう成長し続けていきたいと思います。
修了生の声
I.Yさん(梅花女子大学大学院 現代人間学研究科
心理臨床学専攻出身)
臨床心理士を目指し、大学院へ進学しました。大学院では得るものが大変多く、想像以上にとても充実した濃い2年間を過ごすことができました。学部の時よりも深く心理臨床を学ぶことができるのはもちろんのこと、自らの心に向き合い、心や身体の全体に意識を巡らせて、実体的な経験を通して学ぶことの重要性を実感しました。
本大学院の強みである充実した実習体制において、教育・医療・福祉の3領域全てに携わることができ、実際の現場で臨床心理士としての姿勢やスキルを学ぶことができました。また、1年目から多くのケースを持たせて頂けるため、カウンセリング技術などを身につける経験を積むこともできました。どの実習も決して楽なものではありませんでしたが、座学では学ぶことのできない本当に貴重な体験でした。
楽しいこともたくさんありましたが、上手くいかないことや自分と向きあう過程での悩み・苦しみも少なくはなかったです。それを幾度となく乗り越えられたのも、また、臨床心理士および公認心理師といった二つの資格を取得することができたのも、親身にサポートしてくださる先生方や同じ志をもち、思いを共有できる同期の支えがあったからこそです。大学院で学んだこと・得たものを胸に、これからも日々勉強に励み、心理士として精進していきたいと思います。
附属施設
梅花女子大学大学院
心理教育総合相談センター
本学心理教育総合相談センターは、2004年2月梅花学園豊中キャンパス内に大学院附属施設として開設して以来、相談機関として地域に貢献して参りました。北摂地域をはじめとして広く近畿全域の医療機関や教育機関からの紹介で相談に訪れる方も多く、子どもさんから大人の方まで、幅広い年齢層の方々からのご相談に応じています。 2011年度より、主にうつ病による休職者対象の認知行動療法のプログラムもはじまりました。
また、自閉症などの発達障がいに対して早期から適切な対応をしてほしいという、利用者の皆様のご要望にお応えするべく、発達支援・子育て支援などの子どもの心理臨床のための独立施設として、2008年4月に分室が茨木キャンパス内に開設されました。茨木分室は、中学生以下の子どもさんとその保護者の方々を対象とする、子ども専門の相談センターであり、前述の発達障がいに対する個人・集団療育はもちろん、不登校など、その他さまざまなご相談に応じて、遊戯療法、音楽療法や親面接を行っています。そして、2015年2月より豊中分室と茨木分室を統合し、梅花女子大学大学院 心理教育総合相談センターとして心理的な諸問題により包括的に取り組む体制をスタートさせました。
このように本学では、社会の要請をいち早くとらえ、面接や療育によりよく反映させることができるような、地域に開かれた専門機関としての発展をめざしています。そのために、こころの専門家としての立場をつねに真摯にわきまえ、どのような方々にも対応できるオールマイティな人材を育成しています。
活動実績
- 年間受理件数 平均150件以上
- 年間面接回数 平均2000回以上
大学院生年間担当件数
- 一人当たり面接件数4件以上
- 療育件数1~3件